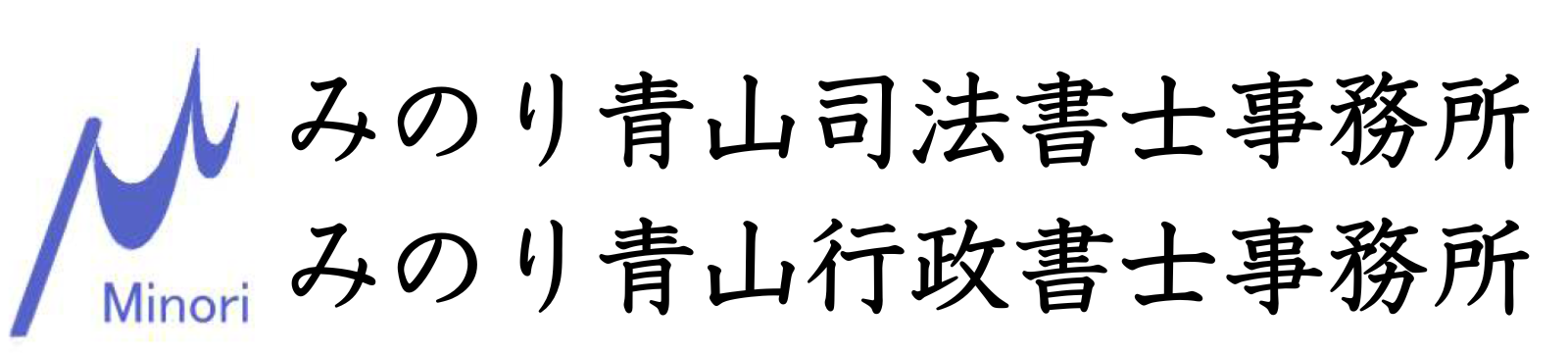特別縁故者とは?
相続が発生すると、通常は被相続人(亡くなった人)の法定相続人が遺産を承継します。
しかし、相続人が一人も存在しない場合、そのままでは遺産は国庫に帰属してしまいます。
このようなときに登場するのが、特別縁故者(とくべつえんこしゃ)への財産分与制度です。
特別縁故者とは、法律用語で「被相続人と生前特別な縁故があった者」のことを指します。
簡単に言えば、法定相続人ではないけれど、被相続人と深い関わりを持ち、生活や療養などで支えていた人に、家庭裁判所の判断で遺産を分け与えることができる制度です。
特別縁故者になれる条件
特別縁故者と認められるためには、以下のいずれかの条件に該当する必要があります。
- 被相続人と生計を同じくしていた
- 被相続人の療養看護に努めていた
- その他被相続人と特別の縁故があった
つまり、単なる知人や親しい友人であるだけでは足りず、生活や療養の面で密接な関わりがあったことが必要です。
ただし、「私は特別縁故者だ」と自己申告しても、家庭裁判所が認めなければ効力はありません。
特別縁故者に該当するかどうかは、あくまで家庭裁判所の判断に委ねられます。
手続きの流れ
特別縁故者として遺産の分与を受けるには、次のような手続きが必要です。
- 相続人不存在の確認
相続人が本当に存在しないかを調査し、家庭裁判所に「相続財産管理人」の選任を申し立てます。 - 相続財産管理人による公告と調査
相続人がいないかを公告し、一定期間待機しても相続人が現れなければ次の段階へ進みます。 - 特別縁故者の財産分与申立て
家庭裁判所に対して「特別縁故者に該当するので遺産の分与を希望する」と申し立てます。 - 家庭裁判所の判断
裁判所が特別縁故者として適格と判断した場合、遺産の一部または全部が分与されます。
もし家庭裁判所が認めなかった場合、最終的に遺産は国庫に帰属します。
特別縁故者になりやすいケース
特別縁故者として認められやすい典型的なケースは以下の通りです。
- 内縁の配偶者(事実婚の妻・夫)
法律上の婚姻関係はないものの、長年同居し生活をともにしてきたケース。 - 事実上の養子
養子縁組をしていないが、生前に親子同然に暮らしていたケース。 - 長期にわたる療養看護をした人
親族に限らず、知人や友人でも、長年にわたり無償で介護や療養を支えていた場合。
具体例
例1:内縁の妻
Aさんには法的な配偶者や子どもはなく、唯一生活を共にしていたのは長年の内縁の妻Bさんでした。
Aさんが亡くなり、相続人が誰もいないと判明したため、Bさんは家庭裁判所に「特別縁故者」として申し立てを行いました。
裁判所は同居や生活実態を認め、BさんにAさんの遺産の一部が分与されました。
例2:療養を支えた友人
Cさんは独身で身寄りがなく、長期入院中に友人Dさんがほぼ毎日病院に通って介護や手続きを手伝っていました。
相続人不存在となった後、Dさんが特別縁故者として申し立てを行い、その貢献が認められ、一定の財産を受け取ることができました。
注意点
- 特別縁故者の制度は「相続人がいない場合」に限られます。相続人が1人でもいれば適用できません。
- 財産分与を受けられるかどうかは裁判所が総合的に判断します。必ず認められるわけではありません。
- 財産分与の対象は必ずしも全額ではなく、一部にとどまることもあります。
まとめ
特別縁故者とは、相続人が一人も存在しない場合に、被相続人と特別な関係を持っていた人に遺産を分与できる制度です。
内縁の妻や事実上の養子、長期にわたり看護した友人などが典型例ですが、最終的に認めるかどうかは家庭裁判所の判断に委ねられます。
「自分は特別縁故者にあたるのではないか」と思う方は、まず家庭裁判所に相談し、相続財産管理人の手続きから進めることが大切です。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
これまでの経験と実績を生かし、各種手続きをを完了までしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続や遺産分割の手続きでお困りの方、ご相談ください。
【初回相談無料】「みのり青山のホームページを見た」とお伝えください。
お問い合わせフォームもしくはLINEからは24時間いつでもご相談受付中です。