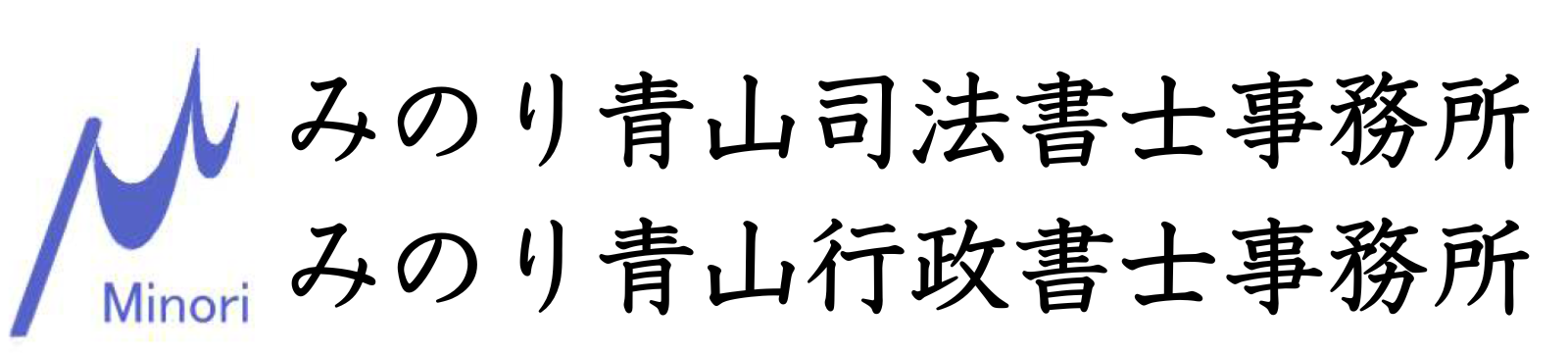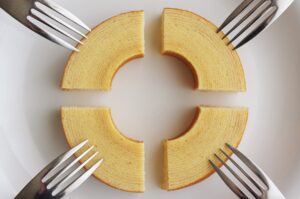たすき掛け遺言とは?子どものいない夫婦におすすめの遺言スタイルと注意点
相続対策を考える中で、「夫婦どちらかが亡くなったとき、残された配偶者にしっかり財産を残したい」という希望を持つ方は多いでしょう。その一つの方法として注目されているのが「たすき掛け遺言」です。
本記事では、たすき掛け遺言の仕組みやメリット、遺言がない場合に配偶者の兄弟姉妹が相続に関わるリスク、実際の文例や注意点について解説します。
たすき掛け遺言とは?
たすき掛け遺言とは、夫婦それぞれが「自分の財産を全て配偶者に相続させる」と定めた遺言のことです。
夫が妻に、妻が夫に、というように財産を掛け合う形になるため、「たすき掛け」という呼び方をされています。
典型例
- 夫の遺言:「私の全財産を妻○○に相続させる」
- 妻の遺言:「私の全財産を夫○○に相続させる」
こうすることで、先に亡くなった側の財産がすべて残された配偶者に集まり、生活の安定や今後の相続の整理がしやすくなります。
遺言がない場合の問題点
遺言がない場合、法定相続に従って相続が進みます。夫婦に子どもがいれば配偶者と子どもが共同相続人となるため、まだ分かりやすいでしょう。
しかし、子どもがいない夫婦の場合、話は少し複雑になります。
この場合、亡くなった人の両親や兄弟姉妹が相続人になります。両親がすでに亡くなっていれば、兄弟姉妹が相続人として登場します。
例えば、夫が先に亡くなったケースで子どもがいないとすると、相続人は妻と夫の兄弟姉妹です。つまり、妻は亡き夫の兄弟姉妹と遺産分割協議をしなければならなくなります。
実務でよくあるトラブル
- 配偶者の兄弟姉妹と疎遠で話し合いが進まない
- 兄弟姉妹の数が多く、全員の署名捺印を揃えるのに時間がかかる
- 遠方に住んでいる、海外にいる兄弟姉妹がいて手続きが長期化する
- 相続分をめぐって争いになる
このようなケースは実際によく起こっており、残された配偶者にとって大きな負担となります。
たすき掛け遺言のメリット
1. 配偶者に確実に財産を残せる
たすき掛け遺言があれば、亡くなった人の財産は全て配偶者が単独で取得でき、兄弟姉妹との協議は不要になります。
2. 生活の安定を守れる
住宅や預金がすべて配偶者に渡るため、生活基盤が崩れる心配を減らせます。
3. 相続手続きがスムーズ
相続人が配偶者だけになるため、名義変更や銀行手続きがシンプルになります。
注意点
遺留分への配慮
たすき掛け遺言は有効ですが、子どもがいる場合には遺留分に注意が必要です。子どもには法律で保障された相続分(遺留分)があるため、遺言によってすべてを配偶者に残そうとしても、後で子どもから請求される可能性があります。
二次相続を考えておく
たすき掛け遺言をすると、最終的に財産はすべて残された配偶者に集中します。そのため、配偶者が亡くなった後(=二次相続)には、相続税や相続人間の分配で別の問題が起こることもあります。あわせて計画しておくことが大切です。
公正証書遺言にしておくと安心
自筆証書遺言でも可能ですが、形式不備で無効になるリスクがあります。実務では公正証書遺言にしておく方が安全です。
まとめ
「たすき掛け遺言」は、夫婦のどちらかが亡くなったときに、残された配偶者に財産を確実に残すための有効な方法です。特に子どものいない夫婦にとっては、配偶者の兄弟姉妹との協議を避けられる大きなメリットがあります。
ただし、遺留分や二次相続の問題にも注意が必要です。実際に作成する際には、専門家に相談して最適な内容に整えておくことをおすすめします。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
これまでの経験と実績を生かし、各種手続きをを完了までしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続や遺産分割の手続きでお困りの方、ご相談ください。
【初回相談無料】「みのり青山のホームページを見た」とお伝えください。
お問い合わせフォームもしくはLINEからは24時間いつでもご相談受付中です。