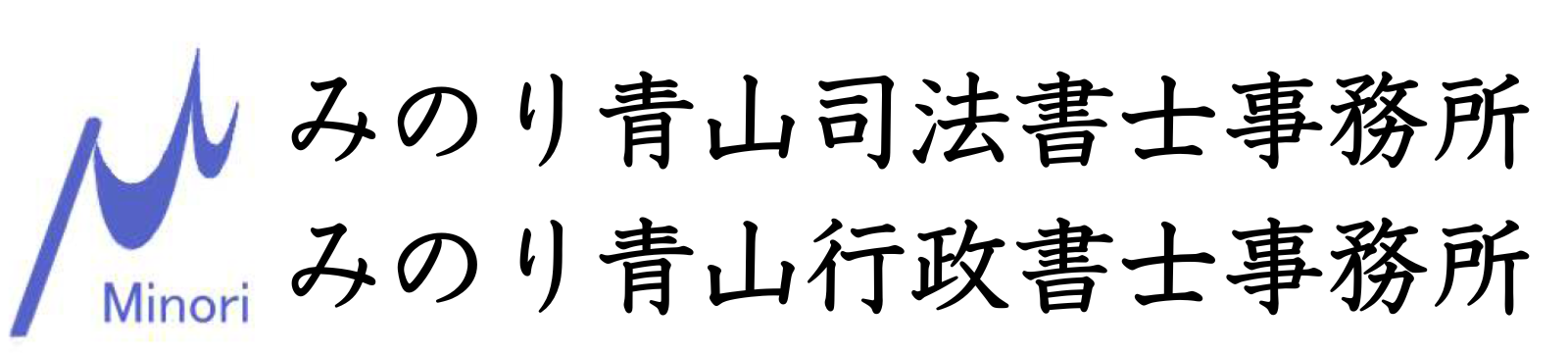相続放棄の活用例|知っておきたい2つのケースと注意点
はじめに
「相続放棄」と聞くと、多くの人は「借金を背負わないために行うもの」とイメージするでしょう。
確かに、被相続人(亡くなった方)に多額の借金があった場合に相続放棄をするケースはよくあります。
しかし実は、相続放棄は「借金があるとき」以外にも、さまざまな場面で有効に活用できる制度です。
今回は、相続放棄をうまく活用する2つのケースと、放棄する際の注意点について具体的に解説します。
1. 次順位の人へ相続させたい場合
相続人は法律で順位が決まっています。
- 第1順位:子(または孫)
- 第2順位:父母(直系尊属)
- 第3順位:兄弟姉妹(代襲相続で甥姪も含む)
たとえば、被相続人に子がいない場合、父母が相続人となります。
ところが、もし父母が高齢で「相続しても活用できない」「管理が難しい」と考えるときはどうでしょうか。
この場合、父母が相続放棄をすれば、次順位である兄弟姉妹に相続権が移ります。
具体例
独身で子のいなかったAさんが亡くなり、母Bさん(80歳)、父Cさん(82歳)、弟Dさん(55歳)が残されました。
本来であれば母と父が相続人ですが、高齢で財産を管理できないと判断し、2人とも相続放棄。
その結果、弟Dさんが相続人となり、自宅や預金を相続しました。
このように「次の世代に直接財産を承継させたい」というときに、相続放棄は有効な手段となります。
2. 遺産分割協議に参加したくない場合
相続が発生すると、複数の相続人がいる場合には遺産分割協議を行います。
しかし中には「他の相続人と連絡を取りたくない」「感情的に関わりたくない」という人もいます。
このような場合、相続放棄を選択することで、遺産分割協議に一切関わる必要がなくなります。
具体例
被相続人Aさんには、子どもが3人いました。
しかし、次男Bさんは長男Cさんと折り合いが悪く、顔を合わせるのも苦痛。
相続財産は自宅と預金でしたが、Bさんは「遺産はいらないから関わりたくない」と考え、家庭裁判所に相続放棄を申述。
その結果、残りの相続人であるCさんと妹Dさんで遺産分割協議を進めることになりました。
このように、相続放棄は「争いに巻き込まれたくない」「関わりたくない」という場合にも使える制度です。
3. 相続放棄の注意点
相続放棄を行う際には、以下の点に注意が必要です。
(1)死亡保険金は受け取れる
相続放棄をしても、死亡保険金は受け取ることができます。
なぜなら、死亡保険金は「受取人固有の権利」とされており、相続財産には含まれないからです。
(2)単純承認と見なされる行為はしない
相続放棄をしても、以下のような行為をすると「相続を承認した」と見なされてしまいます。
- 相続財産を勝手に処分した
- 相続財産の一部を使った
放棄を考えている場合は、財産には一切手を付けずに、まずは家庭裁判所に申述することが重要です。
(3)期限がある
相続放棄は、相続の開始を知ってから3か月以内に行わなければなりません。
この期限を過ぎると、相続放棄はできず、単純承認したと見なされます。
まとめ
相続放棄は「借金を避けるため」だけでなく、さまざまな場面で有効に活用できる制度です。
- 次順位の人に相続させたいとき
- 遺産分割協議に参加したくないとき
ただし、相続放棄には期限があり、また放棄後は一切の権利を失うため、慎重な判断が必要です。
「相続放棄をすべきかどうか」「どのタイミングで行うべきか」に迷ったら、専門家に相談することで、トラブルを未然に防ぐことができます。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
これまでの経験と実績を生かし、各種手続きをを完了までしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続や遺産分割の手続きでお困りの方、ご相談ください。
【初回相談無料】「みのり青山のホームページを見た」とお伝えください。
お問い合わせフォームもしくはLINEからは24時間いつでもご相談受付中です。