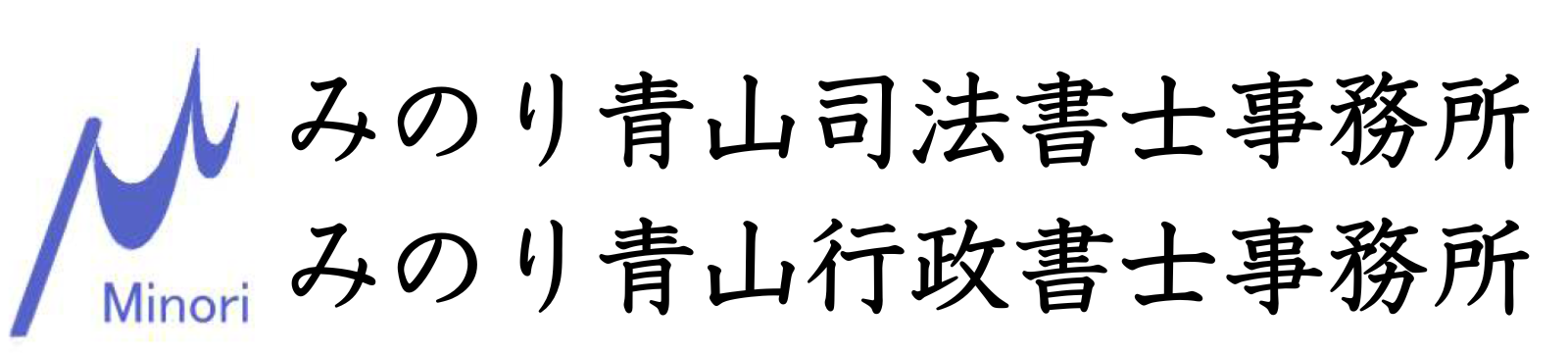寄与分とは?特別寄与者とは?相続における「貢献」が評価される仕組み【具体例つき】
「寄与分」とは何か?
「ずっと親の介護をしてきたのに、相続では兄弟と同じだけ…それって不公平では?」
そう感じる方は少なくありません。
相続は基本的に「法定相続分」に従って分けることになっていますが、相続人の中に被相続人(亡くなった方)の財産の維持・増加に特別な貢献をした人がいれば、その分を考慮して多く遺産を受け取ることができます。
この制度が「寄与分(きよぶん)」です。
寄与分が認められる典型的なケース
- 被相続人の介護や看病を長年続けた
- 被相続人の事業に無報酬で従事した
- 被相続人の生活費や医療費を長期間支援した
- 不動産の維持・管理、借金の返済などで経済的貢献をした
「親子だから助けるのは当然」という範囲を超えて、特別な貢献があった場合に、遺産分割の際に考慮されます。
【具体例①】長女の介護に寄与分が認められたケース
母が亡くなり、相続人は長女と長男。
長女は10年間、母を自宅で介護し、生活全般を支えていました。施設利用や外部ヘルパーは使わず、介護の費用も自己負担。
長男は遠方に住んでおり、ほとんど関与していませんでした。
相続時、長女が寄与分を主張。家庭裁判所での調停により、母の遺産3000万円のうち500万円が寄与分と認められ、残りを法定相続分で分けることになりました。
寄与分を主張するには?
1. 遺産分割協議での合意
相続人全員が納得すれば、寄与分を加味した遺産分割が可能です。
この場合は特別な手続きは不要です。
2. 家庭裁判所に調停・審判を申し立てる
話し合いで解決しない場合は、家庭裁判所に寄与分の申立てを行い、調停や審判で判断してもらいます。
介護記録や費用負担の明細など、客観的な証拠が重要になります。
「特別寄与者」とは?
2019年の民法改正により、相続人でない人でも、被相続人に特別な貢献をした場合に、相続人に対して金銭を請求できるようになりました。
これが「特別寄与者(とくべつきよしゃ)」です。
特別寄与者になれるのは誰?
特別寄与者になれるのは、親族(六親等内の血族または三親等内の姻族)に限られます。
つまり、内縁の配偶者や事実婚の相手など、法律上の親族でない人は対象外です。
対象となる親族の例:
- 子の配偶者(嫁・婿)
- 被相続人の兄弟姉妹の子
- 孫、甥、姪 など
【具体例②】嫁の介護が特別寄与と認められたケース
義父が亡くなり、相続人は長男と長女。
長男の妻(嫁)は、10年以上にわたり義父の介護を担い、通院や食事介助、日常生活の支援をしてきました。
義父が亡くなった後、相続人ではない彼女は遺産を受け取る権利がありませんでしたが、介護の記録や費用の領収書を添えて家庭裁判所に申し立て。
結果、200万円の特別寄与料が認められ、長男・長女がその金額を支払う形となりました。
特別寄与料の請求方法と期限
- 相続開始(被相続人の死亡)を知った日から6か月以内に請求
- 話し合いがまとまらなければ、家庭裁判所に調停・審判を申し立て
- 請求できるのは「金銭のみ」(財産の分割は不可)
寄与分・特別寄与料の注意点
✅ 主観ではなく証拠が大事
「大変だった」「私が支えてきた」という気持ちだけでは不十分。
記録、支出明細、第三者の証言などの客観的な証拠が必要です。
✅ 相続人全員の理解が必要
寄与分を遺産に反映させるには、相続人間の合意または裁判所の判断が不可欠です。
一方的な主張だけで遺産を多くもらうことはできません。
✅ 特別寄与者には限界がある
前述のとおり、親族に限られるため、法律上のつながりがない人(介護士、内縁の妻など)は対象外です。
まとめ|「がんばった人」が報われるための法制度を知っておこう
相続は「平等」が原則ですが、現実には介護や支援をしてきた人が大きな負担を背負ってきたケースもあります。
そうした人の貢献を正当に評価する制度が「寄与分」や「特別寄与者」です。
とはいえ、これらの制度は主張すれば自動的に認められるものではありません。
必要な手続き、証拠、他の相続人との調整が不可欠です。
- 介護記録や支出明細を残しておく
- 話し合いでの解決が難しければ家庭裁判所に申し立てる
- 迷ったら専門家に相談する
「報われる相続」にするために、法制度の正しい理解と、早めの準備を心がけましょう。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
これまでの経験と実績を生かし、各種手続きをを完了までしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続や遺産分割の手続きでお困りの方、ご相談ください。
【初回相談無料】「みのり青山のホームページを見た」とお伝えください。
お問い合わせフォームもしくはLINEからは24時間いつでもご相談受付中です。