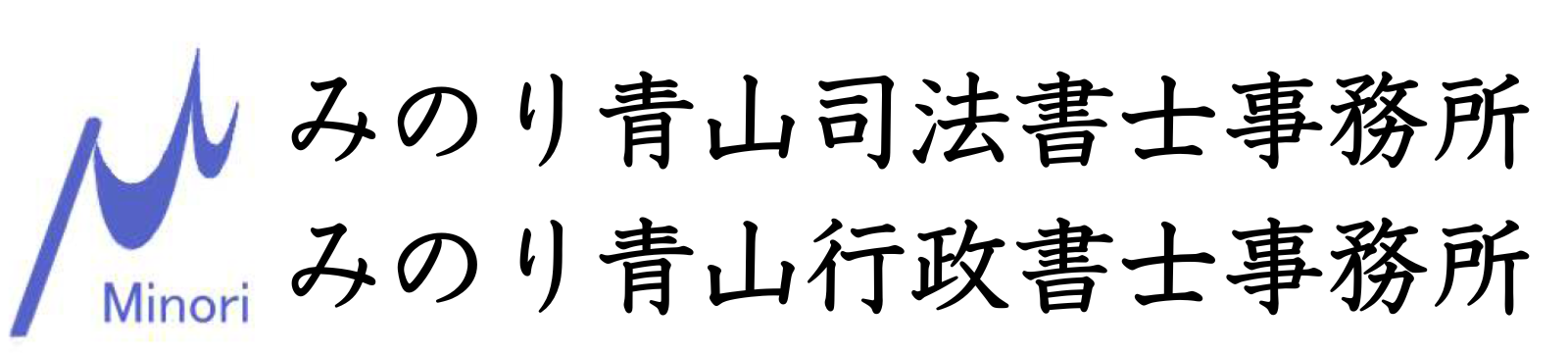共有持分の放棄と相続放棄の違いとは?具体例でわかりやすく解説
「放棄したい」と思ったとき、まず知っておくべき2つの違い
「兄弟と共有名義になっている空き家を自分は使っていない」
「遠方に住んでいて管理や固定資産税の支払いが負担になっている」
「親の借金を引き継ぎたくない」——
こうしたときによく使われるのが「放棄」という言葉ですが、実は「共有持分の放棄」と「相続放棄」では、意味も手続きもまったく異なります。
この2つを混同してしまうと、後から思わぬ負担や責任が発生することもあります。この記事では、それぞれの違いや注意点を、具体例とともにわかりやすく解説します。
共有持分の放棄とは?
「共有持分の放棄」とは、不動産などの共有状態にある財産について、自分の所有権(持分)を手放すことを指します。
たとえば、相続などで兄弟と実家を共有することになったが、自分は遠方に住んでいて管理も関与もできないため、「もう関わりたくない」と思った場合などに選ばれる手段です。
ただし、これは民法255条に基づく法的な処理であり、特別な申請制度があるわけではありません。実務上は法務局で登記を通じて処理される手続きです。
✅ 放棄の方法と登記の考え方
- 放棄は法務局での登記申請によって行います。
- 放棄された持分は、他の共有者に「その持分割合に応じて」自動的に帰属します(民法255条)。
- 放棄者が「誰に渡すか」「割合はどうするか」を指定することはできません。
【具体例】共有不動産の持分放棄
Aさん・Bさん・Cさんの3人兄弟で父の自宅を相続し、3人それぞれ1/3ずつ共有名義となっていました。
Aさんは管理も使う予定もなく、固定資産税の負担も感じていたため、自分の持分を放棄することにしました。
→ Aさんが法務局で持分放棄の登記を申請すると、その持分(1/3)は民法の規定により、残る共有者Bさん・Cさんに「各自の持分に応じて」自動的に帰属します。
この例ではB・Cがともに1/3ずつ持っていたため、放棄された1/3がそれぞれに1/6ずつ加算され、結果として2人はそれぞれ1/2の持分を取得することになります。
※なお、無償で持分を得る行為は税務上「贈与」とみなされる可能性があるため、贈与税の申告が必要になる場合があります。
相続放棄とは?
一方、「相続放棄」は、相続開始後に、財産も借金も一切引き継がないとする明確な法的手続きです。
民法第938条に基づき、家庭裁判所に申述することで、最初から相続人でなかったことになると法律上扱われます。
✅ 手続きのポイント
- 相続を知ってから3か月以内に、家庭裁判所に相続放棄を申述。
- 裁判所に受理されれば、プラスの財産もマイナスの財産(借金)も含めて、一切の相続を拒否できます。
- 他の相続人に相続が移るため、関係者間の調整が必要になる場合もあります。
【具体例】借金の多い親の相続放棄
Dさんの父が亡くなったあと、預金はほとんどなく、借金が数百万円あることが判明。
→ Dさんは「借金を引き継ぎたくない」と考え、相続開始を知ってから2か月以内に家庭裁判所へ相続放棄を申述。
申請が受理され、父の遺産も借金も一切引き継がないことに。
表で比較|2つの「放棄」の違い
| 比較項目 | 共有持分の放棄 | 相続放棄 |
|---|---|---|
| 対象 | 所有している不動産の持分など | 相続全体(財産・債務) |
| 手続き先 | 法務局(登記) | 家庭裁判所(申述) |
| 効果 | 他の共有者へ持分が比例配分される | 最初から相続人でなかった扱いになる |
| 手続き期限 | なし(いつでも可能) | 原則3か月以内 |
| 債務への影響 | 債務は残る可能性がある | 債務は完全に免責される |
| 税務の注意点 | 贈与税がかかる可能性あり | 相続税の課税対象外(放棄したため) |
よくある誤解に注意
❌「持分放棄すれば借金も関係なくなる」は誤解
すでに相続人となって取得した財産について、たとえば「持分を放棄したからもう相続は関係ない」と考えるのは誤解です。
共有持分の放棄は、相続放棄のように借金から免れる効果はありません。借金を完全に避けたい場合は、相続放棄の申述が必須です。
状況に応じた正しい選択を
- 相続が始まったばかりで借金が多い → 相続放棄
- すでに共有名義の不動産を持っているが、管理や関与をやめたい → 共有持分の放棄や売却
まとめ|言葉は似ていても、意味も手続きもまったく違う
「共有持分の放棄」と「相続放棄」は、いずれも「放棄」という言葉を使いますが、その内容は根本的に異なります。
- 相続放棄:家庭裁判所で行い、財産も借金も一切放棄できる
- 共有持分の放棄:法務局で登記を行い、他の共有者に自動的に持分が移る
誤った判断で不利益を被らないよう、自分の状況に合った手続きがどちらなのかを冷静に見極めることが大切です。
不安なときは、専門家に早めに相談してみるのも方法です。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
これまでの経験と実績を生かし、各種手続きをを完了までしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続や遺産分割の手続きでお困りの方、ご相談ください。
【初回相談無料】「みのり青山のホームページを見た」とお伝えください。
お問い合わせフォームもしくはLINEからは24時間いつでもご相談受付中です。