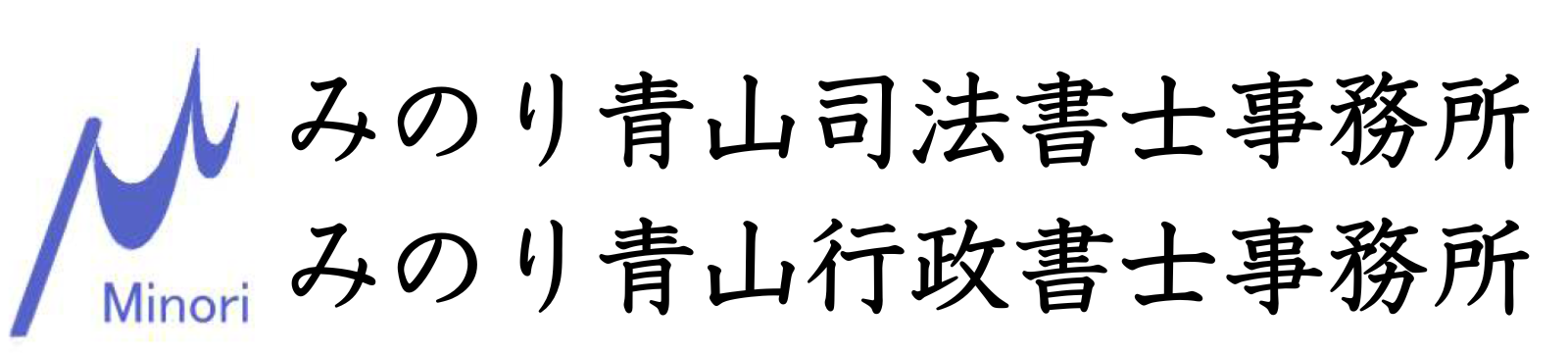「うちの親は元気だし、まだ遺言なんて早いよな…」
そう思っていても、ある日突然やってくるのが“相続”の現実です。
だからこそ、親が元気な今、少しずつ相続や遺言の話をしておくことが、後の安心とスムーズな手続きにつながります。
この記事では、親に遺言書を書いてもらったほうがよい理由と、その伝え方・注意点・公正証書遺言を勧める理由について解説します。
なぜ、親に遺言書を書いてもらうべきなのか?
親が亡くなったあと、相続人(通常は配偶者や子どもたち)で遺産をどう分けるか話し合う必要があります。
このとき、親の「意思」が残されていないと、家族間でトラブルが起きやすくなるのが現実です。
実際に起こるトラブル例
- 「長男が家を継ぐと思ってたのに」
- 「介護してた私が少なすぎる」
- 「疎遠だった兄弟が突然口を出してきた」
- 「通帳や土地の名義がどうなっているかわからない」
遺言書があれば、親の意志が明確に残り、家族間の不信感を防ぎやすくなります。
親が元気なうちに遺言書を作ってもらうことで、相続手続きはぐっとスムーズになります。
遺言書の基本|種類と特徴
遺言書には主に2種類あります。それぞれの特徴を押さえておきましょう。
自筆証書遺言(じひつしょうしょゆいごん)
- 親が自筆で作成するもの(全文を自分で書く必要あり)
- 2020年から法務局での保管制度が始まり、保管すれば検認不要
- 無料で作れるが、書式不備によって無効になるケースも
✅ メリット:手軽で費用がかからない
⚠️ 注意点:形式の不備、紛失、勝手に破棄されるリスクがある
公正証書遺言(こうせいしょうしょゆいごん)
- 親が内容を公証人に伝え、公証役場で正式に作成する
- 原本は公証役場に保管され、紛失や改ざんのリスクなし
- 費用は財産の内容や人数によって数万円〜十数万円
✅ メリット:法的に確実で無効になるリスクがほとんどない
⚠️ 注意点:作成には手間と費用がかかる
なぜ公正証書遺言がオススメなのか?
遺言書を作成するときには、公正証書遺言をおすすめするケースが多いです。以下がその主な理由です。
① 無効になる心配がほとんどない
自筆証書遺言は、書き方を間違えると無効になります。
一方で公正証書遺言は、法律の専門家(公証人)がその場でチェックしながら作成されるため、安心です。
② 原本が安全に保管される
公正証書遺言は、公証役場で原本が保管されるため、紛失や改ざん、隠蔽のリスクがありません。
③ 家族全体が安心できる
子ども世代からすると、「あとで揉めたらどうしよう…」という不安がつきものです。
公正証書遺言があれば、「わざわざ公正証書の形で遺言を残した」という親の明確な意思が形になっているので、兄弟間でも納得が得られやすいのです。
④ 手続きがスムーズになる
遺言があると、遺産分割協議が不要になったり、金融機関での相続手続きが迅速になります。
つまり、親の死後の事務処理の負担が大きく減るのです。
親に遺言の話をどう切り出すか?
「遺言書を書いて」と言い出すのは難しいもの。
時期を見計らうのが大事ですが。タイミングや言い方の工夫をご紹介します。
スムーズな切り出し方のコツ
- 自分も終活の話を始めていると伝えてから話を振る
- 「家族に迷惑をかけたくないってよく聞くけど…」と一般論から入る
- 「最近こういう本読んだよ」と本やニュースを話題にして会話の入口にする
よくある親の反応と対処法
- 「まだ元気だし、必要ないよ」→「元気なうちだからこそ準備しておけるんだよ」
- 「そんなの縁起でもない」→「確かに。でも、後の人が困らないようにね」
- 「子どもたちに任せればいい」→「残された人の負担が大きいからこそ、意志を残してほしいんだ」
自分の遺言も意識してみる
この記事をきっかけに、自分自身の将来の準備も考えてみませんか?
「親の遺言の話をきっかけに、自分もエンディングノートを始めた」という方も多くいます。
50代は親の終活に向き合うタイミングであり、同時に自分の人生の次の段階の始まりでもあります。
まとめ|遺言は“家族を思う行動”のひとつ
親に遺言書を書いてもらうのは、決して財産のためだけではありません。
それは、家族の思いを大切にするための対話であり、準備です。
親が元気な今こそ、まずは話題にすることから始めてみましょう。
📌 今日からできる一歩
- 親との昔話をきっかけに会話を広げる(「あの家って、いつ買ったんだっけ?」など、思い出話から自然に導入すると、実家や将来の話にもつなげやすくなります。相続の話題が重く感じられるときは、こうしたきっかけが効果的です。)
- エンディングノートを自分で買ってみる(まずは自分用にエンディングノートを買ってみましょう。「自分も書いてみたんだけど、意外と役に立つよ。一緒にやってみない?」と親に見せれば、関心を持ってもらいやすくなります。)
- 相続・遺言に関する無料セミナーを親に紹介する(自治体や地元の専門家が開催するセミナーは、第三者の話をきっかけにできる良いチャンスです。「こういうのあるけど行ってみない?」と軽く誘うと、話しやすい雰囲気を作れます。)
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
これまでの経験と実績を生かし、各種手続きをを完了までしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続や遺産分割の手続きでお困りの方、ご相談ください。
【初回相談無料】「みのり青山のホームページを見た」とお伝えください。
お問い合わせフォームもしくはLINEからは24時間いつでもご相談受付中です。