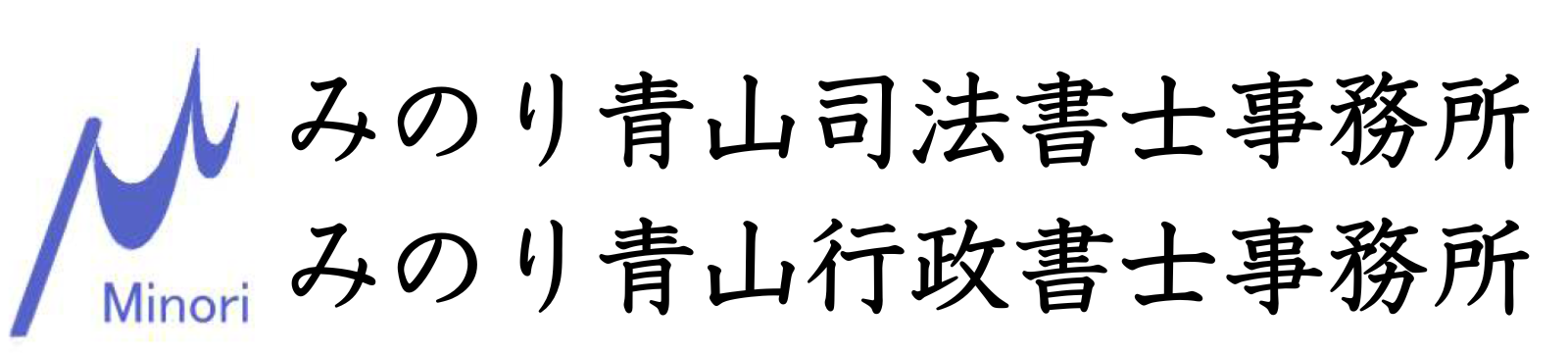相続放棄・限定承認とは?相続トラブルを防ぐための選択肢と注意点【事例つき解説】
相続放棄とは?
相続放棄とは、被相続人(亡くなった人)の財産や借金を一切相続しない手続きです。
民法上、相続人は相続の開始を知った日から原則3か月以内に「単純承認」「相続放棄」「限定承認」のいずれかを選ばなければなりません。
相続放棄は家庭裁判所に申述書を提出し、受理されると「初めから相続人でなかった」とみなされます。
これにより、相続財産のすべて(プラスもマイナスも)から離脱することになります。
限定承認とは?
限定承認とは、「プラスの財産の範囲内で借金を引き継ぐ」相続方法です。
つまり、相続によって得た財産を限度として借金を返済し、それを超える債務があったとしても、相続人が自腹で払う必要はありません。
「財産の全貌がわからない」「もしかすると借金のほうが多いかも…」といった不安がある場合には、限定承認という選択肢があります。
ただし、相続人全員の同意が必要であり、公告や清算などの手続きも複雑なため、実務ではあまり活用されていないのが現状です。
相続放棄と限定承認の違いと選び方
| 比較項目 | 相続放棄 | 限定承認 |
|---|---|---|
| 財産の扱い | 全て放棄(何も受け取らない) | プラスの範囲で借金を返済 |
| 借金の引継ぎ | 一切なし | 一部引き継ぐ(超過分は返済不要) |
| 手続きの難易度 | 比較的簡単 | 複雑(相続人全員の合意が必要) |
| 主な利用ケース | 借金が多い/関わりたくない | 財産内容が不明で損をしたくない場合 |
✅ どちらを選ぶべき?
- 「借金しかない、関わりたくない」→ 相続放棄
- 「財産はあるが借金もあるかもしれない」→ 限定承認
共通の注意点|どちらも慎重な判断が必要
- 期限は3か月以内:原則として、相続開始を知った日から3か月以内に家庭裁判所へ申述が必要です。
- 放棄後の行動に注意:相続放棄をしても、遺産の一部を使ってしまうと「単純承認」と見なされ、放棄が無効になることがあります。
- 例:預金の引き出し、車の名義変更など
- 限定承認は特に手続きが複雑:財産目録の作成、官報公告、債権者への弁済など、専門知識が必要となるため、司法書士や行政書士への相談が推奨されます。
【事例①】放棄の連絡がなく、次順位に借金が移ったケース
父が亡くなり、相続人は長男・長女・次男の3人。
父の事業に関わる借入金があることを知った長男は、すぐに相続放棄を決意し、家庭裁判所に申述しました。
ところが、長男はそのことを他の兄弟に伝えておらず、次男が自動的に「次順位の相続人」となったことに気づいたのは、すでに3か月が過ぎた後。
結果、次男は放棄の機会を逃し、借金の返済義務を負うことに…。
→ 相続放棄は「個人の意思」でできる手続きですが、可能であれば他の相続人へ情報共有したほうが後のトラブルを防ぐことができます。
【事例②】不動産の相続を望んだが、借金が多くて限定承認を選択
母が亡くなり、相続人は長女と長男の2人。母名義の郊外の住宅を長女が相続して住み続けたいと希望していましたが、母には多額の借金がある可能性があると判明。
財産の内容が不明だったため、2人は専門家に相談し、限定承認を選択。
公告や債権者への対応など手続きは複雑でしたが、不動産を守りながら借金リスクを最小限に抑えることができたケースです。
よくある質問(Q&A)
Q. 相続放棄をしたら、他の家族に伝える必要はありますか?
A. 法的な義務はありませんが、トラブルを回避する観点からは伝えるのがおすすめです。
放棄した事実を知らずに次順位の相続人が手続きを進めてしまうと、知らないうちに借金を引き継いでしまう危険があります。
Q. 限定承認は1人だけでできますか?
A. できません。
相続人が複数いる場合、全員で手続きを進めなければならず、1人でも反対すると成立しません。
Q. 相続放棄を撤回できますか?
A. 原則、撤回できません。
一度受理された放棄は法的に確定し、「やっぱり財産がほしい」と思っても取り消せないのが原則です。
まとめ|借金のある相続には「知識と備え」が不可欠
相続放棄や限定承認は、「借金を背負わないための制度」としてとても重要です。
ただし、手続きの期限や方法、周囲への影響まで配慮しなければ、逆にトラブルを招くこともあります。
- 財産の内容がよくわからない
- 借金がありそうで不安
- 兄弟との連絡がとれない
こうした不安がある場合は、できるだけ早く専門家に相談することが大切です。
相続放棄・限定承認は、「知っているかどうか」があなたと家族を守るカギになります。
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
これまでの経験と実績を生かし、各種手続きをを完了までしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続や遺産分割の手続きでお困りの方、ご相談ください。
【初回相談無料】「みのり青山のホームページを見た」とお伝えください。
お問い合わせフォームもしくはLINEからは24時間いつでもご相談受付中です。