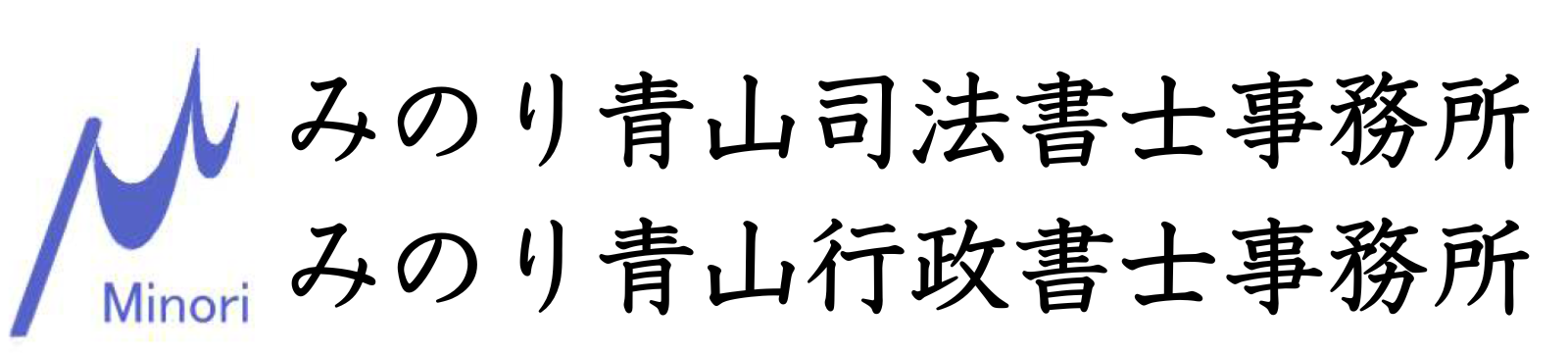目次
法定相続分とは?
法定相続分とは、民法で定められた**相続人ごとの取り分(割合)**のことです。
遺言がない場合、相続人同士で遺産を分ける際の「基準」となります。
法定相続分の基本ルール
相続人の組み合わせによって、法定相続分の割合は次のように定められています。
1. 配偶者と子が相続人の場合
- 配偶者:1/2
- 子ども:1/2(人数で均等に割る)
例)子どもが2人 → それぞれ1/4ずつ
2. 配偶者と直系尊属(親など)の場合
- 配偶者:2/3
- 直系尊属:1/3(人数で均等に割る)
例)両親が健在 → 父と母でそれぞれ1/6ずつ
3. 配偶者と兄弟姉妹の場合
- 配偶者:3/4
- 兄弟姉妹:1/4(人数で均等に割る)
例)兄弟2人 → それぞれ1/8ずつ
子どもがいない場合の注意点
子どもがいない場合、親や兄弟姉妹が相続人になるケースがあります。
ただし、親も兄弟もすでに亡くなっている場合は、甥・姪が相続人となることもあります。
子どもが亡くなっている場合(代襲相続)
本来相続人になるはずの子がすでに亡くなっている場合は、その子(被相続人から見て孫)が相続人となります。これを「代襲相続(だいしゅうそうぞく)」といいます。
法定相続分はあくまで基準
法定相続分は、遺産分割協議の「スタート地点」となる考え方です。
相続人全員が同意すれば、実際の分け方は自由に決めることができます。
ただし、意見が割れた場合や話し合いがまとまらない場合は、家庭裁判所での調停や審判となり、原則として法定相続分に基づいて判断されることが多くなります。
まとめ
- 法定相続分は民法で定められた相続の取り分の目安
- 配偶者は常に相続人となり、相手に応じて割合が変わる
- 子や兄弟が亡くなっている場合は代襲相続が発生する
- 実際の分割は相続人の話し合いで自由に決定できる
みのり青山では、相続や遺産分割のお悩みや手続きの進め方に関して、初回相談無料で対応しております。
対面での面談がご心配な方や、遠方で直接お会いすることが難しい方、受付時間内にお時間が取れない方にも、お気軽にご相談頂けるように各種オンラインツール(ZOOM、LINEなど)を利用しての面談にも対応しております。
これまでの経験と実績を生かし、各種手続きをを完了までしっかりとサポートいたしますので、お気軽にお問い合わせください。
相続や遺産分割の手続きでお困りの方、ご相談ください。
【初回相談無料】「みのり青山のホームページを見た」とお伝えください。
お問い合わせフォームもしくはLINEからは24時間いつでもご相談受付中です。